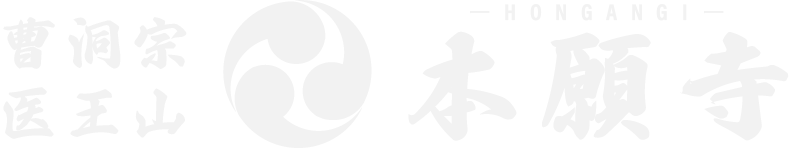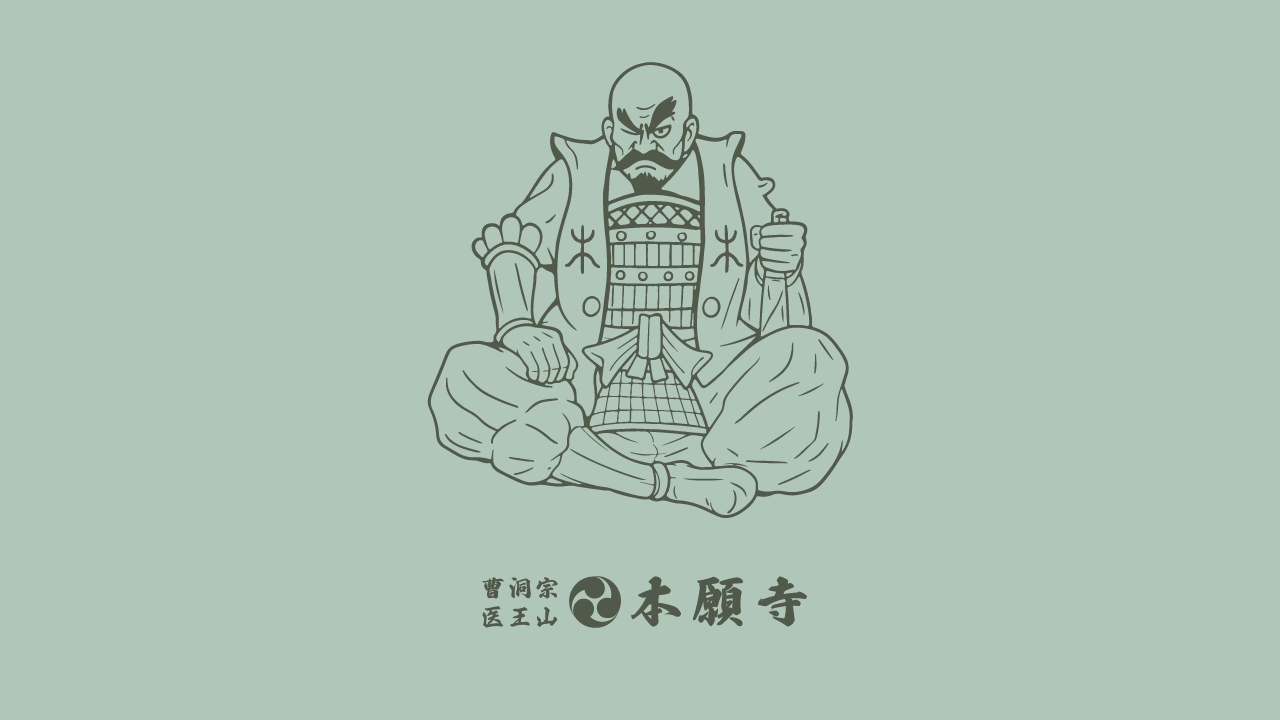武田信玄を支えた智将
戦国時代を語るとき、必ず名前が挙がるのが「甲斐の虎」武田信玄。その信玄を陰で支えた名軍師が山本勘助です。勇猛果敢というよりも、知略に優れた“頭脳派”。だからこそ「智将」と呼ばれ、今も人々を惹きつけています。
波乱に満ちた半生
勘助は今川家臣の家に生まれ、幼い頃は「源助」と呼ばれていました。その後大林家の養子となり、名を「勘助春幸(かんすけはるゆき)」と改めます。若いころには各地を渡り歩き、兵法や築城術を学びながら腕を磨きました。
一度は駿河の今川義元に仕官を願い出ますが、伝承によれば「容姿がよくない」と断られてしまったとか。隻眼や足の不自由といった説も残ります。もしここで受け入れられていたら、歴史は大きく変わっていたかもしれませんね。
武田信玄との出会い
五十歳近くになって、ついに甲斐の若き武将・武田晴信(のちの信玄)に見出されます。破格の待遇で迎え入れられた勘助は、信濃攻略や川中島の戦いで知恵をふるい、その名を轟かせました。
特に有名なのが「啄木鳥戦法(きつつきせんぽう)」です。軍を二手に分け、一方を敵の背後に回して奇襲、正面からは信玄が攻める――まさに木をつつくキツツキのような作戦でした。残念ながら上杉謙信に読まれて大乱戦となり、勘助自身もこの戦で命を落としたと伝えられています。それでも彼の名は、知略の象徴として後世まで語り継がれています。
謎多き人物像
勘助の姿は史料によって描き方が異なります。片目で足が不自由だったという話もあれば、ただの「三河出身の兵法家」とだけ記されるものもあります。生まれた地も三河説、駿河説と複数あり、今も決着はついていません。
そんな謎めいた部分こそが、人々の想像をかき立て、大河ドラマ『風林火山』などで繰り返し取り上げられてきた理由でしょう。さらに、戦場で相手の動きを先読みしたことから、現代の「ヤマカン(山勘)」という言葉の語源になったとされるのも面白いところです。智将の名が、今も私たちの会話の中に息づいているのです。
豊橋・賀茂本願寺のゆかり
豊橋市賀茂町にある賀茂本願寺は、勘助ゆかりの地のひとつ。境内には勘助の父母の墓があり、案内板や観音像が訪れる人を迎えています。周辺には「勘助生誕の地」と刻まれた石碑も建ち、賀茂町が生誕地候補とされる理由を物語ります。
境内は自由に参拝でき、豊川駅や名鉄豊川稲荷駅から車で15分ほど。周辺には高さ2メートルを超える槇の生垣が残り、落ち着いた街並みを散策することができます。静かな空気の中で、勘助の時代に思いを馳せるひとときは格別です。
史跡を訪れて
今川家に拒まれても諦めず、努力を重ねて武田信玄に仕えた山本勘助。その姿は、現代を生きる私たちにも「挑戦を続ける勇気」を教えてくれます。賀茂本願寺を訪れ、その足跡に触れてみませんか。歴史の鼓動とともに、勘助の生き様がきっと心に響くはずです。